菊間小は、「基礎的で汎用的な読解力の育成」に全教科で取り組んでいます📚
大量の情報があふれる時代には、情報を速く正確に読み取る力が必要です。
この土台が、自ら学ぶ力につながっていきます🌝
この日、本校の学力向上アドバイザー:椿原正和先生(教授法創造研究所)の特別授業がありました。
物語文を、登場人物の言動だけに着目し、場面ごとの図にまとめます(図読法)。



昨年も指導を受けている3年生は、グループで相談しながら図を完成させることができました😀
そして、図をもとにあらすじを話します。
一人で発表するのは、緊張します。
でも、椿原先生の「緊張するときに、成長するのです」という後押しに、とても頑張りました。
45分間で、全6場面を完成させてしまった3年生、すごいですね🧡


劇団四季のミュージカル公演😲
大迫力の歌、芝居、音響、道具、に子どもたちは大興奮でした。
さらに、メッセージ性のある物語にも子どもたちは深く感動し😢
豊かな心の成長につながりました😊

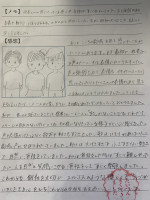
その後は、学校へ帰る途中で内緒の寄り道❕
天気が良かったので🌞
瓦のふるさと公園でお弁当を食べて遊びました😊
また1つ良い思い出ができました✨



「生活を支えるお金と物」の学習を、担任、栄養教諭とともに行いました🌶
担任がScratch(スクラッチ)で作成したプログラムでバーチャルお買い物をします😃
<条件>
・4人分の量
・肉、じゃがいも、たまねぎ、にんじん、カレールウ、お茶
・2,000円以内


カレールウは複数のメーカーが設定され、お茶も大小あり、
その他、様々な選択肢がある中、グループで話し合いながら決定していきました。
決めた理由を尋ねると・・・・・・
・新鮮 ・産地 ・安全 ・表示 ・好み ・アレルギー ・量
・値段 ・食品ロス(食材の廃棄)
たいへん良く考えていることが分かりました✨
菊間調理場のSDGsの取組についても学び、買い物名人3か条をまとめました🍛


避難訓練(予告なし)を実施しました📢
<条件> 児童への予告はしない。
<想定> 授業中に1回目の地震、その1分後に2回目の地震が発生。



これまでの避難訓練でも、菊間っ子は真剣に取り組んでいました🤔
しかし、命を守るためには「真剣さ」「本気度」のレベルを上げなければなりません。
最近は「防災能力は、基礎学力」と言われています。
保健委員会では、石けんの補充や献立の紹介等の常時活動に加えて、毎月目標を決めて活動しています👐
2月の目標は、「話を聞くときは、姿勢を正そう」です。
今月は教室に行き、正しい姿勢について、お手本を見せながら説明しました🌟



机とおなかの間は、グー✊1つ分!
足🦶の裏をぺタッとつける!
背中🙎♂️はピン!
「グー・ペタ・ピン」の姿勢で、素敵な菊間っ子になってほしいです🥇
「漢字の組み立て」の学習です。
最初は、漢字の組合せゲーム😃
漢字の基本となる部分(部首)に気が付きました👌
教科書を指差したり言ったりしながら、「かんむり」「あし」「たれ」などを何度も確認💫


続いて、ペアで協力して、部首ごとに漢字集めをしました
どのペアがどんな漢字を集めているか、ロイロノートで共有💻すると、
ライバル心に🔥がついたようです。



太陽石油株式会社様の御寄附による「テントの天幕」が納品されました。
早速、運動場で使ってみました。
真っ白な天幕がきれいです。😂
下校前の5・6年生に紹介したところ、みんな嬉しそうでした。
運動会で、保護者や地域の皆様に改めて御披露いたします。✨


1年生も2年生も、3年生も4年生も、5年生も6年生も、みんな頑張った学習発表会👨👩👧👦






保護者や地域の方も、おおぜい来てくださいました💞💞

菊間っ子の成長を、ともに喜んでくださってありがとうございました。
5年生
5年生が坊ちゃん劇場「鶴姫伝説」を観覧しました🎥
8Kの映像で、まるでその場で演技されているような迫力ある上映でした🎶



映像を見て、平和であることは決して当たり前のことではないと考える子が多かったです🎗
また、演劇を見て、自分たちも劇をするときにはこんな風に演技したいと思いをはせていました💭
この経験も次へ次へと繋げていきましょう😁
最強寒波により、南予などでは大雪に見舞われた昨日、
愛媛マンダリンパイレーツ⚾の選手・スタッフが、交通安全指導・挨拶運動をしてくださいました🧡


球団マスコットキャラクター「マッピー」 、太陽石油ブランドキャラクター「ソラトくん」も駆けつけ、
菊間っ子も、いつもにも増して、笑顔の登校となりました😃🥰

